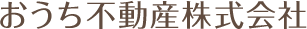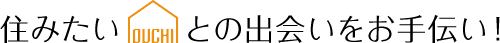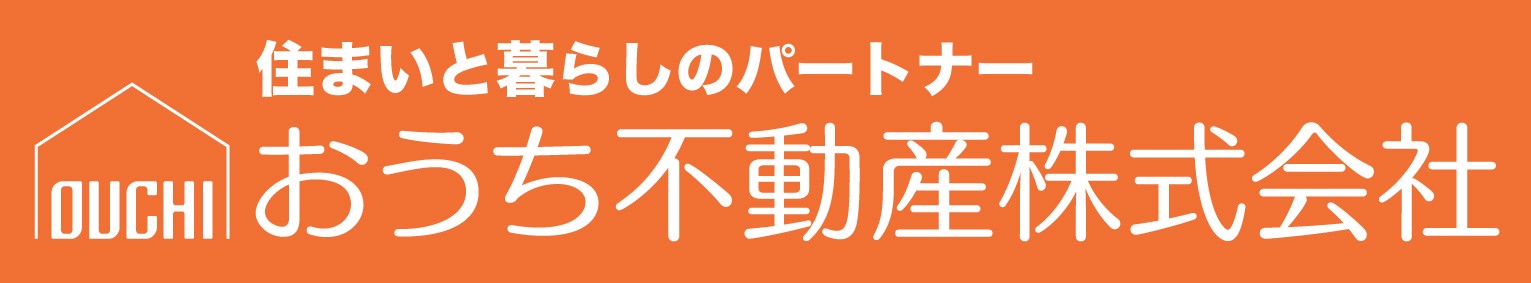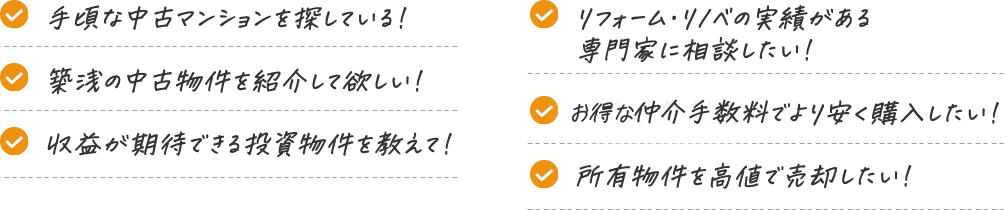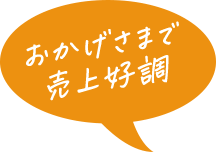東京メトロ有楽町線・副都心線 「地下鉄赤塚駅」駅・街の歴史編

毎回、都心のさまざまな「駅」に焦点を当て、その周辺エリアの住みやすさや街の便利な情報をお届けしている当「タウン情報」ですが、今回はガラッと趣向を変えて、以前好評だった「おかわり企画」をお送りいたします。
その企画とは、今までに登場したエリアをさらに徹底解析し、アクセス環境や住まい環境、駅・街の歴史などの項目別に特集しちゃおう!というもの。
そして登場するのは、当タウン情報ではもはやおなじみの「東京メトロ有楽町線・副都心線」から特徴的な名称を持つ「地下鉄赤塚駅」です。
では、さっそく「駅の歩み」からスタートです!

地下鉄赤塚駅
今、このエリアで住まい購入を検討中の方へ特別なお知らせ
🔍【物件一覧をチェック】(別タブで開きます)
「地下鉄赤塚駅」の歩み
以前、当タウン情報でこの「地下鉄赤塚駅」エリアを取り上げた際には「板橋区」の分類として取り上げましたが、これは駅名にも採用されている「赤塚」という地名が「板橋区」に含まれているから、というのが大きな理由でした。
当タウン情報は、そもそも「不動産に関連する」情報を発信をしていることもありますので、物件エリアから見れば確かに「板橋区」として取り上げる方が正しいといえます。
しかし、厳密に言えば、こちらの駅は「練馬区内に存在する鉄道駅」でもあり、駅の大部分は「練馬区北町八丁目」に存在していますので、今回の記事は便宜上「練馬区」としての扱いにさせていただきました。
さて、ちょっと長めの前置きから本題である「駅の歩み」に入っていくと、こちらの駅を含む「東京メトロ有楽町線」区間が営業を開始したのは1983年(昭和58年)のこと。
もちろんその当時は、運営会社名称に伴った「営団赤塚駅」という名前で登場したのですが、このように「営団」から「地下鉄」へ冠名が変わった(2004年(平成16年)、東京メトロへの業務継承に伴う変更)駅には、他にも「地下鉄成増駅」がありますね。

駅出口
この2つの駅が「地下鉄を関する理由」については、前回の「地下鉄赤塚駅」の回でもご紹介していますので、興味の湧いた方はそちらもご覧ください。
もうひとつ、この駅の大きな特徴となるのが「駅間わずか100mほどの所に東武東上線の「下赤塚駅」が存在する」という点ですが、この2駅2路線には「駅の歴史」という点において「営業開始時期に50年以上の大きな差」があります。
ですので、もし詳細な「駅や路線の歴史」を知りたいと考える人は「下赤塚駅の歴史についても知る必要がある」といえるかもしれませんね。
さらに興味の湧いた方は、当タウン情報の「下赤塚」の回も参考にして見てくださいね?
まずは「練馬区北町」を知ろう! ~駅周辺の街の歴史~
ではさっそくセクションタイトルにもあります通り、駅の大部分が存在する「練馬区北町」について進めていきましょう。
この「北町」ですが、実は「一丁目から八丁目まである」というなかなか広大なエリアでありまして、もともとは旧「川越街道」の一角である「下練馬宿」として栄えたエリアでした。
当然、江戸時代から続く宿場町ですから、非常に多くの人々が行き交っていた場所ではあるのですが、実際には「宿」とついていても文字通り「宿泊」する利用者はあまり多くなく、どちらかといえば「休憩場所」としてにぎわっていたそうです。

この当時「下練馬村」に属していたこのエリアは、時代が下るにつれ「北豊島郡練馬町」とその名前が変わりますが、現在の「北町」になるきっかけとなったのは1932年(昭和7年)の「板橋区編入」によるもの。
この時、それまで使用されていた「練馬町」は3つに分割され、それぞれが「練馬」を関した「練馬北町・練馬仲町・練馬南町」と名乗ることになったのだそうです。
そして、戦後にはこの「練馬」が外れることになり、現在の「北町」という地名に変化していきましたが、この直前の「昭和初期〜戦前」にかけて、大規模な「耕地整理」が実施されており、ちょうど1940年(昭和15年)におよそ一万坪の広大な地域を「東京第一陸軍造兵廠練馬倉庫(現在の自衛隊練馬駐屯地)」として使用されることにもつながりました。
これらの状況も重なったおかげか、旧「練馬町」で唯一、現在も「北町」として残るようになったのですね。(仲町は「氷川台」へ、南町は「桜台」へ改称となり、元の地名は消滅しています)
戦後となって間もない1947年(昭和22年)には、皆さんもごぞんじの通り、旧「板橋区」より「練馬区」が独立していますので、この「北町」という地名は旧「練馬町」であった「板橋区」時代を今に伝える「レガシーネーム」ともいえるでしょう。
続いては「板橋区赤塚新町」側についても深く掘り下げてみましょう。
続いて「板橋区赤塚新町」を知ろう! ~駅周辺の街の歴史②~
現在、「地下鉄赤塚駅」の北側は「赤塚新町」という町名となっていますが、ここに登場する「赤塚」という地名、そのルーツはなんと「鎌倉時代」からあったといわれています。
実際の文献上で「赤塚」の地名が確認されるのは「室町時代」からですが、それ以前に「赤塚氏」という鎌倉武士の一族が居たことから、ルーツは「鎌倉時代」と言われるようになったのだそうです。(諸説あり、地名とは関係ないともいわれている)
そして、この「室町時代」以降は「赤塚六ヶ村(あかつかろっかそん)」として広く知られるようになりますが、「6つの村(正確には、上赤塚、下赤塚、成増、徳丸(本)、徳丸脇、四葉の各村)」ということもありその範囲は非常に広く、現在の「成増」や「徳丸」「四葉」などの地名も当時の「赤塚六ヶ村」がそのルーツといえるでしょう。
江戸時代になるとこれらの6村は、その大半がそれぞれ「江戸幕府」により「天領」とされますが、明治に入ってもそのつながりは消えず、1889年(明治22年)に全てが合併し「赤塚村」へと変わります。

駅前周辺の様子
さらに1932年(昭和7年)の旧「板橋区成立」時には、この「赤塚村」が再分割され、それぞれ「上赤塚町、下赤塚町、成増町、徳丸本町、徳丸脇町、四ッ葉町」というようになっていきました。
最終的には、これらの6町の内「上赤塚町、下赤塚町、徳丸町、四葉町」の4町から一部が組み合わさって、現在の「赤塚新町」を構成するようになり、今に至るというわけです。
これだけ由緒正しい「赤塚」の地名は、約700年の時を超えて今に伝わっていますから、地元住民ならずとも今後も末永く残して行きたいと感じるのではないでしょうか?
今後どうなる?「北町・赤塚新町」が歩む道とは?
最後のセクションは、魅了的な要素が目白押しの「北町・赤塚新町」の今後を、この記事をまとめつつ一緒に考えてみましょう。
前述の通り、この「地下鉄赤塚駅」に残る「赤塚」という地名は、遠い昔の時代から受け継がれてきていますが、実はさらに昔の「旧石器時代」から集落が存在していたことがほぼ確実視されており、「人間の住まい」としては、まさに「折り紙付き」の超優良エリアといっていいでしょう。
もちろん「コロナ禍」以降の時代においてもその伝統は続いており、「今の不動産のトレンド」ともいえる「郊外志向」にもピッタリとハマる人気エリアです。
しかも、最初のセクションでもご紹介した通り、駅からたった100mほどの「下赤塚駅」を利用することで、実質的に「東京メトロ有楽町・副都心線」の他に「東武東上線」も利用でき、まだまだ大多数を占める「職場への出勤が大前提となる職業の方」にもオススメできる「アクセス性の高さ」も手に入るでしょう。
あえてデメリットを挙げていくならば「幹線道路付近では交通量と騒音が激しい」という点や「ラッシュ時は「東武東上線」付近に「開かずの踏切」が数多く存在する」という点などがありますが、それらを差し引いたとしても「この地に住む恩恵」が薄れるほどではないでしょう。
・お気軽にお問い合わせください
今後、時代が進むほどにその人気を高めそうな雰囲気すら感じられる「地下鉄赤塚駅」エリアにご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽におうち不動産までご相談ください。
専門のスタッフが丁寧に対応し、最適な物件をご提案いたします。
【周辺関連情報】
・練馬のお隣駅「中村橋」は高レベルの極上「穴場」エリア!Vol.1
・練馬のお隣駅「中村橋」は高レベルの極上「穴場」エリア!Vol.2
・住みやすさ・アクセス良好!!三路線利用可能な「小竹向原」駅
【関連周辺情報】
・地下鉄赤塚駅とは目と鼻の先の「下赤塚駅」の暮らしやすさは?
・有楽町線・副都心線の始発駅♪「和光市駅」の住みやすさとは!?
・公園も多くファミリーにも単身にも最適な東武東上線「下板橋」駅の魅力とは!?
・都心が持つ良さが凝縮された「中板橋」は、住まい探しの「超・穴場」である!
地下鉄赤塚駅周辺地図
地下鉄赤塚駅周辺の学区域情報
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000388.html
(板橋区役所ホームページより)
地下鉄赤塚で利用できる路線
東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」
東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」
東武東上線 「下赤塚駅」
戸建て(新築戸建て・中古戸建て)でもマンション(中古マンション・リノベーションマンション)でも、お客様のご希望条件に合わせて多数ご紹介できます!東京23区を中心に首都圏で気になる物件が あればご相談下さい。
当エリアの公開中物件一覧はこちらから
(2024年8月追記)